|
|
文化は宗教を必要とするか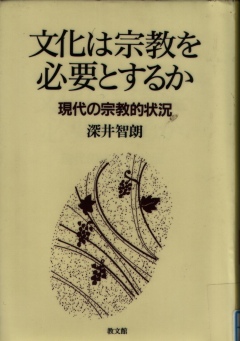 ( 現代の宗教的状況 ) ( 現代の宗教的状況 )
プロローグ 弁証学としての文化の神学
( 「国営教会」と「自由教会」 )
「国教会」とは「国営教会」という言葉からも明らかなように、国の統治機構の一部に組み込まれ、国家予算の中に組み込まれ、官僚機構化した教会のことである。
「自由教会」とは自発的な結社であるから、そこに集まる人々の共同体であり、人々の寄付によって営まれる民間団体である。
一七世紀のピューリタン革命の中で生じた宗教システムのラディカルな転換とは、「国営教会」からの分離や、それとの対決という意識をもった「自由教会」が登場したということであろう。それは宗教システムの民営化、市場化であったと言ってよい。
国営教会の時代にはひとつの行政システム、ひとつの国営教会という原則であったが、「自由教会」の発生は、さまざま自発的な結社の並列化を可能にしたのであり、そこには「宗教的な市場」が生じたからである。
国営教会は分裂ではなく、統一のための社会システムであるが、「自由教会」は市場化しているために、自由競争の原理によって分裂と競争を繰り返してきている。
国営教会の存在は、既に述べた通り「宗教の国家的独占状態」である。コンスタンティヌス一世によるキリスト教公認以来、キリスト教はヨーロッパにおいていわば宗教における独占集団であり続けた。これを「コンスタンティヌス体制」と呼ぶことができるであろう。それは教会と国家との一致、あるいは「一つの国家」=「一つの教会」という原則に基づいた教会体制と言ってよいであろう。
マルティン・ルターの宗教改革もまたこの原理を破壊することはできなかった。元来宗教改革とプロテスタント教会の出現は、この独占状態を破壊するはずであったが、大陸の宗教改革の帰結は、ルター派教会の領邦化、あるいは「領主の信仰がその土地の信仰になる」という、コンスタンティヌス体制の細分化による継続であったからである。
(句読・改行等、便の為に当サイトにて添加)
池田会長・創価学会による、“自己保身”と“選挙の票”欲しさによる「国立戒壇」放棄と、それを正当化するための二冊の「悪書」に見られる“現行憲法に仏法を合わすべし”とするような「法義歪曲」の顛倒見・詭弁は、もちろん論外なことでありました。
日蓮大聖人の御抄から“仏法上”、御遺命が「国立戒壇」に帰結することは、素直に了解されるべきでありましょう。同時に、“世法上”の問題としての宗教システムの民営化・市場化という事態の進行が、現代において“必然”ともいうべき事柄に属することは、また承知すべきことでしょう。
<世俗の辺>において、どうしても「宗教の国家的独占状態」が不可欠であるのか、あるいはそうではない方途があり得るのかという<問い>・<議論>は、しかるべくなされるべきでありましょう。
( 平成十四年十二月十二日、櫻川
記 )
戻る 次
|
|
|