|
|
文化は宗教を必要とするか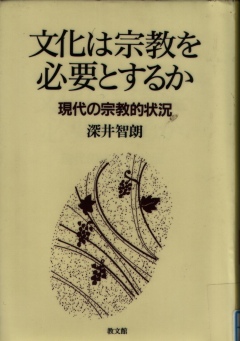 ( 現代の宗教的状況 ) ( 現代の宗教的状況 )
プロローグ 弁証学としての文化の神学
( 「宗教における「民営化」 )
このような状況を打ち破る現象は、宗教改革のさらなる展開を待たねばならなかった。アングロサクソン世界に展開したプロテスタンティズムの歴史的経験がそれである。
一七世紀のピューリタンのいわゆる分離派の教会論の中にそのような動きを見ることができるであろう。
彼らはあくまで「国教会制度」の保持を主張する国王側に対して、自覚的な信者の集団を形成し、その制度の中から出て行った。それはいわば「宗教における私的企業」、あるいは「民営化」である。
このような集団が複数存在するところでは、当然「宗教の独占状態」は終焉を迎え、「宗教団体」の市場が誕生することになる。すなわちピューリタンの教会は、その地域に誕生する他の「私的団体」である教会と市場において争うのである。あるいは独占状況を保持し続けようとする国営教会を批判し、いわば宗教的市場に介入しようとする国家を批判したのである。
「国教会」から「自由教会」が生じるというこの歴史的なモデルは、実は近代社会があらゆるところで経験していることではないだろうか。
日本の例でいうならば、近年の民営化論、すなわち国鉄の民営化に始まり郵政事業の民営化論や介護保険における試み、あるいは電話通信システムの多元化は、これまで国営企業として独占的な活動を続けてきたものたちが、一企業として、複数の企業が参加する市場において争うという出来事である。そこには競争が生まれることになる。
(句読・改行等、便の為に当サイトにて添加)
世間においても出世間においても“競争”なき処、必ず“癒着”と“停滞”と“官僚化”が進展することは、たしかなことでありましょう。
さて、宗教的市場における“競争”には、種々の局面やレベルがあることでしょう。しかして、その競争の“根源的フェーズ”においては、他宗や異文化に向けての「宗教批判」が如何なる“説得力”を持ち得るか、が重要な鍵をにぎることでありましょう。
すなわち、相互の「宗教批判」における“競争”において“説得力”を持つためには、どうしても「学問」の領域における「根拠」が、また必須となることでしょう。
「学的根拠」はもちろん、“十分条件”ではあり得ませんが“必要条件”であることは、たとえば”仏滅年代”や“大乗非仏説”等における実際の“論争の現場”において、ただちに明白となることでしょう。
( 平成十四年十二月十五日、櫻川
記 )
戻る 次
|
|
|