|
|
権力者の心理学
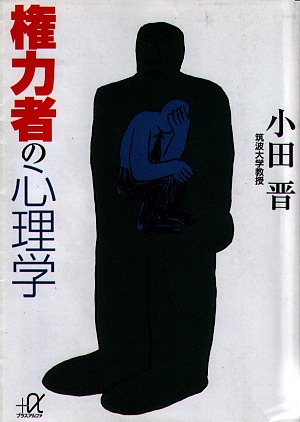
第一章 指導者の心理学
10 指導者がもつサバイバル遺伝子
血縁による相続にこだわる心理
(略) 江戸時代から、わが国の大きな商家では(場合によっては大名の家でさえ)、後継者にふさわしい息子を育てることは至難であり、それに失敗した場合は、廃嫡して、養子によって相続させることが普通に行われていた。
二〇世紀も終わりに近づいた今日、政治家も、経営者も、医師も、むしろ以前にも増して、血縁者、それも核家族内部での継承にこだわるようになったのは、ひとつには、おそろしいほどの相続税の圧力が、株主権や財産だけの相続をほとんど無意味にしている
ということもあるかもしれない。
また、新しい民法が 家督相続の制度を廃止したので、実子を排除した形での、養子のメリットを少なくしている
ということもあるかもしれない。
何よりも、政治家や経営者自身の心の中から 抽象的な「家」の観念が姿を消し、核家族単位の血縁の中にしか相続の意味を見出せなくなっており、いわば社会生物学的には、先祖返りをしたような現象が見られる
ということになるのであろう。
そうであるとするなら、大企業の経営のような能力を要する仕事を、血縁による相続によって引き継ぐということは、かなり困難な作業である。
官僚化している今日の企業組織では、二代目、三代目の経営者は、必ずしも、初代のオーナー経営者と同じ形での経常能力を備えている必要はないけれども、ともかく「無難に君臨している」ということでさえ、さほどに容易なことではない。
それが成功するには、ひとつには、当人のむしろ性格的な資質と、第二に家族内の関係、第三に企業内部の人的な布置という 三つの条件がそろっていなければならない。(略)
とりわけ、二代目、三代目の経営者で、父親の経常する企業以外に勤務したことがないという場合には、人生において、「横並び」の関係をもつことが少ない。
かつて、堤康次郎氏(西武コンツェルンの創始者)は、息子の義明氏に「友だちはつくるな。おまえが助けることはあっても、助けられることはない」と教えたという。
( 句読・改行等、便のため当サイトにて添加 )
戻る 次
|
|
|