|
|
仏教手ほどき ( 仏教手保登記 )
其四、本門の戒壇
( 事の戒壇の御遺命 )
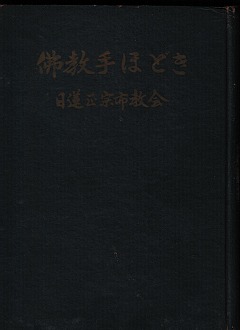
然り而して此事の戒壇堂建立の地点につきては、念の為の御妙判の明文を列記し奉りて決して之が身延山や其他の地点にあらざることを明かに致しませう。
夫につきて先づ御書五大部を拝見しますに、立正安国論は天下諌暁の御書にて一家の規範でありますが、唯是れ権実相対の御法門のみで、三大秘法の事につきては何事も仰せられてはありません。
開目抄はどうかと申ますと、之は広く五段の教相を明かにせられ、最後種脱の相対をも明かにせられたるも、一念三千の法門は唯法華経本門寿品の文の底に秘し沈むとのみ仰せられて、三大秘法の御名をも秘して仰せられず、撰時抄はどうかと申ますと、撰時抄は天台未弘の大法経文の表に顕然たりと迄判じ給へども、其天台未弘の大法は果して如何なる大法なるかを露はし給はず、三大秘法の御名・尚秘し給ひてありまず。
然らば報恩抄はどうかと申ますと、報恩抄に来りますと、正しく「問云・天台伝教の弘通し給ざる正法ありや、答云く有り・求云く何物ぞや、答云く三あり」等と示し給はれて、本門三大秘法の名言のみならず、具に本門の本尊の形貌並に本門の題目等をも判釈遊ばされたれとも、独り戒壇の一事に於て唯其名義のみを挙げ給ひて形貌をは宣(のたま)はせられず、法華取要抄亦然りであります。
然るに弘安四年に至り太田禅門に対する三大秘法抄中に具に戒壇の相貌を示し給ひて宣はく「戒壇ト者王法仏法ニ冥シ仏法王法ニ合メ、王臣一同に本門ノ三大秘密の法を持チて、有徳王覚徳比丘の其乃往を末法濁悪の未来ニ移サン時、勅宣並ビニ御教書を申シ下シて霊山浄土ニ似タラン最勝ノ地ヲ尋テ戒壇ヲ建立ス可キ者か、時ヲ待つ可キ耳。事の戒法と申スは是也。三国並に一閻浮提の人懺悔滅罪の戒法のみならず、大梵天王帝釈等も来下して踏給フベき戒壇也」と、茲に始めて戒壇の形貌を明言し給はれてあります。
然るに未だ之にては霊山浄土に似たらん最勝の地とのみにて、未だ其地点を明言し給はれざりしが、弘安五年壬午九月聖祖御入滅近きにありと知しめし給ひ、日興上人に対して聖祖一期の弘法を御付嘱あらせらるると同時に、明かに本門戒壇堂建立の地点を明示せられてあります。
即ち「国主此法ヲ立テ被ハ富士山ニ本門寺ノ戒壇ヲ建立被ル可キ者也。時ヲ待ツ可キ而、事ノ戒法卜謂フハ是也」と。
鳴呼聖祖一期の弘法は整然として起尽があります。三大秘法は実に聖祖一期の大事なれば、容易に之を宣言し給はざりし事、三大秘法抄の結文に「予年来己心ニ秘スト雖 此法門を書キ付て留メ置ずんば門家の遺弟等定メテ無慈悲ノ讒言ヲ加フ可シ」と仰せられてあるを見ても伺はれるのであります。
殊に戒壇の一事は愈々聖祖の御理想実現の終極・御滅後の大事なれば容易に之を宣言し給はず、漸く御滅後の御年日興上人に対して其地点を明言遊ばされたのであります。
諸君・本門戒壇堂建立の地点の身延山にあらずして富士山なること、明々白々一点の疑問なきでありませう。
彼の日興上人が身延の謗法地を退去し給ひて富士山の麓(ふもと)上野郷に大石寺を建立して茲に本門の大御本尊を安置し奉れることの偶然ならざることよくよく鑑考すべきことであります。況んや富士の山腹に戒壇堂建之の予定地を卜して六万坊を建立すべき天母ヶ原と云う大原野を選定せられたること、師弟不二・唯仏与仏の御境界にまします日興上人にして始めてなし給はれし御事であります。
( 句読・改行等、便の為に当サイトにて添加 )
これ、池田会長が国立戒壇を放棄し宗門がそれに随順するまでは、異論のない富士の伝統法義でありました。
それがいとも易々と曲げられてしまった要因は、創価学会による宗門支配の巧妙さと、宗門の油断・腑抜けに求められるべきでありましょう。
むしろ創価学会側としては、かくも強固な富士の伝統法義を変更することの困難さを、十分に承知していたことでした。
ゆえに、その当事者の一人・原島元教学部長は「妙信講の浅井昭衛氏らとの六回にわたる話合いが行われました。これは国立戒壇をめぐる、いわば「論争」ともいうべき性格をもっていました。だいたいこの論争自体がこちらに有利なはずはありません」(池田大作先生への手紙)と述べています。
また山崎元顧問弁護士も、この冨士の伝統法義をして「日蓮正宗の教義の中で最重要なものであった。キリスト教における“神の国”にも匹敵する思想である。それを根本から変更するのである」(盗聴教団)と述べていることからも、それが知られます。
しかして当時の宗門はほとんど、強大な創価学会におんぶに抱っこの状態といっても過言ではないことでありました。さながら保護者であり庇護者であるかのように、そして何とも眩しく格好よく輝いて見えた創価学会が池田会長が、よもや宗門に悪いようにはするはずがないだろうといった依存的にして安易な思いが、当時の宗門のすみずみにまで浸透していたことでした。それは当時の宗門の機関誌等をひもといてみるならば、瞭然でありましょう。
(
平成十四年二月二十五日、櫻川 記 )
戻る
|
|
|